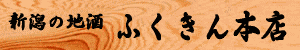| |
写真をクリックすると拡大写真がご覧になれます |
|
| |
 |
酒米は蒸して使います。
これは、生の白米でんぷん(βでんぷん)を、麹カビが糖に分解しやすい形(αでんぷん)に変化させるためです。また、麹カビは米の水分含量が35〜40%位のときにもっとも繁殖しやすいので、「炊く」のではなく「蒸す」のです。
私たちがお米を食べるときは「炊く」のですが、水分は65%位にもなり、麹の繁殖には水分が多すぎます。 |
|
| |
 |
蒸しあがったお米を取り出します。
洗米から浸漬まで、ストップウォッチを片手に時間を計り、水分量を管理するのも、この蒸しあがったお米の水分含量が麹カビの繁殖に最適の条件となるようにするためです。 |
|
| |
 |
蒸しあがったお米は取り出されて、このような「放冷機」で適温まで冷まされます。
以前は布の上で自然冷却されていましたが、今はこのように強制空冷されます。
蒸米は、麹米や掛米といった目的別に分けられ、それぞれの適温まで冷されます。
麹米は「麹室(こうじむろ)」に運び込まれます。 |
|
| |
 |
麹室は、麹カビの生育に適した温度・湿度に保たれています。通常は35度以上、約60〜75%程度です。
ここに運び込まれた蒸米は、布をかけて2〜3時間ほど置いてなじませ、続いて薄く広げて種付けの準備をします。 |
|
| |
 |
いよいよ、種付けです。
杜氏さんの真剣な顔つきをご覧ください。
種麹をバランスよく均等に振りかけるのに神経を集中させます。米1粒に、種麹が5〜6粒位が着くのが良いとされています。
「1麹、2もと、3造り」と言われるように、麹造りは日本酒の製造工程中でもとりわけ重要で、酒の品質を決めるとも言われています。 |
|
| |
 |
種麹をまいて、1昼夜ほどたった頃でしょうか。
麹カビの活動が盛んになってきて、蒸米の温度が上昇してきます。この温度を調節するためにへぎ(麹蓋)に小分けします。
温度管理が大変重要になってきます。 |
|
| |
 |
それからさらに数時間がたちました。
麹カビの活動がもっとも活発になります。
蒸米の温度が上昇してくるので、かき混ぜ、広げておきます。拡大写真を見ると3本のへこみが入っているのがわかります。
このようにして、熱、炭酸ガス、水分を放出して麹カビの成長を調節します。 |
|