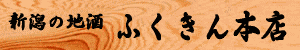| |
写真をクリックすると拡大写真がご覧になれます |
|
| |
 |
これがなんだかわかりますか?---「酵母」です。
この酵母の働きで、糖がエチルアルコールに変化してお酒になります。
これ以降の工程では、麹カビがお米のでんぷんを糖に変え、酵母がこの糖をアルコールに変えるという変化が平行して起こります。このため、「平行複発酵」と呼ばれています。 |
|
| |
 |
水、麹、酵母を混ぜた水麹と呼ばれるものの中に、蒸米を入れていきます。「酒母」造りです。
仕込みに使うタンクは、ご覧のようにかなり小さめです。
この酒母は「もと(元、または酒へんに元と書く)」とも呼ばれるように、これからのお酒造りの元となり、酒質の良し悪しを決定付ける大切な要素となっています。 |
|
| |
 |
酒母の発酵の様子の拡大写真です。
ここでは、水分バランスと温度管理がポイントとなります。約2週間をかけて、酵母を大量かつ純粋に強く成長させます。
この酒母造りに使われる蒸米は全体の7,8%くらいと少ないものです。 |
|
| |
もろみ製造 |
酒母に、蒸米、麹、水を混合したものを「もろみ」と呼びます。この工程では、1度に原料(蒸米、麹、水)を入れずに、何回かに分けて仕込んでいきます。このような仕込み方を「段仕込み」と呼び、通常は3回に分けるために「3段仕込み」と呼ばれます。
大吟醸のもろみの発酵日数は通常30日程度です。しかし、「越乃景虎」では、45日ほどかかります。仕込み水を含めた蔵癖のためで、酒質を追求した結果です。 |
|
| |
 |
これは「雫(しずく)しぼり」の様子です。
こうして人手をかけて、ひとつひとつの袋にもろみを入れて、竹の棒につるしていきます。これだけ小さな袋に入れてゆくのですから、何枚の袋が必要になるのでしょうか・・・とても手間のかかる方法です。
布目から自然に落ちるお酒だけを集める、最高に贅沢な搾り方です。 |
|
| |
 |
ずらりと並んだお酒の袋・・・別名「首吊り」とも言うそうで・・・
圧力をかけずに搾るということは、まだまだ袋の中にお酒が入っている状態で、絞りをやめてしまうということ、、、出てきたお酒は、まさにエッセンスと呼ぶにふさわしいものです。
「越乃景虎 大吟醸秘蔵雫酒」、「越乃景虎 純米大吟醸雫酒」、「越乃景虎 大吟醸雫酒」はこの方法でしぼられます。 |
|
| |
 |
搾られて出てきたお酒です。
ぜひ、拡大写真をご覧ください。とっても美味しそうでしょう!!!のどが鳴りそうです。
インターネットで、味も香りもお伝えできれば良いのですが・・・こればかりは・・・ |
|