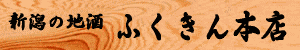| |
写真をクリックすると拡大写真がご覧になれます |
|
| |
 |
こちらは、槽(ふね)で搾っています。
こちらもひとつひとつ人手を使ってもろみを袋に入れ、丹念に並べて積み重ねられます。この時、槽の垂れ口から最初に出てくる白濁したお酒のことを「荒走り」といいます。
搾りの工程を「上槽」とも言いますが、このように槽(ふね)で搾ることからきています。 |
|
| |
 |
積み重ねられた袋を、上からゆっくりと力をかけていきます。搾りの工程は、このように圧力をかけることから「圧搾」とも呼ばれています。
一般酒の場合はこのように手間をかけず、「薮田式圧搾機」を使います。これは、蛇腹のようになっている所にもろみを入れて、アコーデオンのように縮めて搾るもので、自動化できて人手がかかりません。 |
|
| |
 |
搾られたお酒が少しずつでてきます。
こちらも拡大写真をご覧ください。勢いはありませんが、これまた美味しそう・・・
槽口(ふなぐち)から出てきたばかりの無濾過生原酒・・・蔵でしか飲めないお酒で、本当に美味しいですよ! |
|
| |
 |
ずらりと並んでいるのは、斗瓶(とびん)です。この1斗(10升)入る瓶に入れて貯蔵、熟成させることを「斗瓶囲い」と言います。この瓶には鑑評会用の大吟醸が入っております。
通常は貯蔵タンクで貯蔵、熟成させますが、「斗瓶囲い」は熟成の進行具合や質が違ってきます。小分けしなければいけないので手間がかかりますが、それだけのことはあります。 |
|
| |
 |
斗瓶から、お酒を取り出しています。「斗瓶囲い」は手間がかかりますね。
斗瓶は7・8度の低温管理された部屋で貯蔵されますが、1本1本熟成具合が微妙に違ってきます。 |
|
| |
 |
火入れです。
日本酒にとって有害な微生物(特に火落菌)を殺すとともに、お酒の中に残っている麹・酵母を破壊して香味を調整し、保存性を高めます。65℃前後と比較的低温で加熱するために、お酒の風味が損なわれると言うことはありません。
この写真は鑑評会用の大吟醸のやり方で、一般には管を通る際にお酒が加熱されるようになっていて、人手がかからないようになっています。 |
|
| |
 |
火入れをした後、氷の中に入れて急冷します。
これは、お酒が長い時間温かいままになって、だれてしまわないようにするためです。
写真は鑑評会用大吟醸のやり方ですが、吟醸以上の「越乃景虎」はこれと同じ効果があるように、火入れの後、急冷のための冷蔵庫に移されます。 |
|
| |
 |
鑑評会用大吟醸が出来上がりました。
杜氏さん自らが、丁寧に瓶詰しております。
何気なく飲んでいるお酒ですが、こんなにも人の手がかかり、時間がかかるものなのです。
大量生産では出せない味を求めて、新潟の中小の蔵は努力しつづけています。 |
|